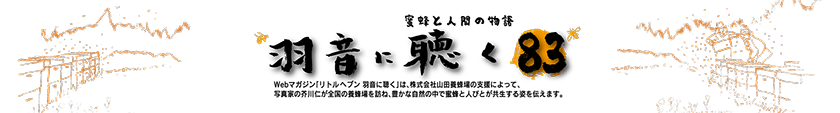子どもを捨てよっとじゃなか

純一さんが蜂の状態を確認し、珠江さんに蜜巣板を持ってくるように声を掛ける
「親父が戦争から帰って来て、林業の手伝いに行っていた時に養蜂をしていた方と出会ったそうですよ。その方の弟子に付くようにして始まったんです。うちの養蜂は……」
純一さんの父、秀雄さん(ひでお・2010年9月に82歳で亡くなる)が創業した高見養蜂場では、毎年11月20日を目処に本拠地の北海道滝川市から長崎県五島市(福江島)へ蜜蜂群を越冬させるために移動している。福江島では草刈りなど蜂場の整備や移動してきた蜜蜂群の内検を済ませると、12月20日頃には一旦北海道に帰って正月を迎え、2月上旬まで滞在する。生まれ育った風土の中で子どもや孫たちとゆっくり過ごせ、蜂たちは長崎県の離島で越冬中なので、この2か月足らずの北海道での生活が体力的にも精神的にも一年間で最も余裕のある期間なのだ。
「私は一人息子なもんですから、大学まで行かせてもらいましたけど、夏休みは北海道で採蜜の手伝いをして、春休みは鹿児島で越冬の手伝いをする約束でした。もちろん小学校に入るまでにも両親に蜂場に連れて行かれていましたからね。蜜を採る時には朝3時半とかの出発で……。大学を卒業したら、そのまま養蜂に入ったんです。父は30年くらい前から鹿児島県の大崎町に越冬に行っていたと思うんですけど、当時は農家が菜種油を採っていましたから菜の花が一面に咲いていました。けれど、私が養蜂に入った昭和53(1978)年頃から農家が菜の花を作らなくなって、蜂の餌になる花粉さえも足らなくて黄な粉を与えてみたりして、大学を卒業した頃の越冬は父の時代と比べると大変でしたね」

継ぎ箱から単箱に巣板を移動させる前にバーナーで内側を焼いて消毒してから使用する
純一さんが47年前を思い出している。それから4年後、純一さんが26歳の時にお見合いをして、19歳の珠江さんと結婚する。
「何にも分かんないで何とかやってきたけど、じいちゃん(義父)が『蜂はやさしく扱えばやさしくなる』と言っていたけど、ある人に言わせると『あんたんとこの蜂は荒い』って……」と珠江さんが大笑いする。「蜂んとこ(蜂場)では喧嘩しないね」と純一さんの顔を見て、珠江さんが続ける。「蜂が嫌いだったら(この仕事は)できなかったですね。春になって蜂が増えていくのを見ていると、何か良い感じ……。でも、子どもが居なかったら、ここまでできなかったなあと思うことは沢山ありますね。足下に長男の朋樹(ともき)を寝かせながら、長女の和江(かずえ)を抱っこしてたよね。いつだったか茶箱の中に長男を入れて、長女を蓋に寝かせて採蜜していたら、地元のおばあさんが2人で来て『あんたら子どもを捨てよっとじゃなかっですか』と怒ったように言ってきたことがあったですね。家一軒ない山の峠のような蜂場で「もうちょっとだよ」と子どもらに声を掛けながら待たしていたんですけど、子どもを放り出しているように見えたのか『なにしてんの』って、おばあさんたちが……」。待った無しの採蜜時には子どもたちをゆっくり世話するゆとりがなかった頃を振り返る珠江さんの言葉に、後悔と子ども達への深い愛情が滲み出る。
結婚した頃から純一さんの福江島行きが始まっている。父親が蜜蜂を越冬させていた鹿児島県の大崎町に行き、一旦父親の蜜蜂群を手伝った後で、自分が担当する蜜蜂群をトラックに積み込んで福江島へ移動するのだ。
「福江島に来ていた養蜂家が島にはもう行かなくなると聞いて、蜂場を譲ってもらったんですけど、その当時本土と福江島を運航していた九州商船から『蜂を積んだトラックは乗せられない』と言われて、トラックから巣箱を船の甲板に一旦下ろし、島に着いたら又トラックに積み込む作業をしていました。昭和62(1987)年頃まで積み替え作業は続きましたね。福江島へ渡るフェリーが五島汽船になってからは巣箱を積んだままトラックで乗船できるようになって楽になりましたけどね」
「その当時だったよね、トラックで先に帰る純一さんを見送るので、(長男の)朋樹と一緒に港で泣いたよね。長男が生まれてから6年間ほど、そんな生活していたよね。でも、その次の年からはもう朋樹は来ていないんです。小学校に行くようになったもんだから……」
「もうすぐ70歳、26歳から43年間」と、純一さんが感慨深そうだ。「5月になって北海道へ帰る途中、新潟県辺りでフェーン現象か何かで、道中で40(群)も50(群)も蒸殺(巣箱内の温度が上がり過ぎて蜂が死ぬこと)してしまったりするとがっかりしますね。福江島では採蜜はしないんです。椿とからし菜は3月一杯で花は終わりになるかな。商品化するほど蜜源がないですよ」

基本的な役割分担はあるが、必要な時には2人で力を合わせる
Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi