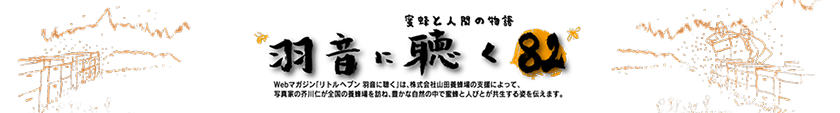ひと冬寝かせた貯蜜はメインディッシュ

加藤蜂場 それぞれが養蜂家として一人前の仕事を順繰りに進めていく
事務所で蜜蜂群の大きな年間の流れについて聞いた後、午前中は桑名市内の加藤蜂場と午後は山村蜂場で、2月10日に売り蜂を80群出荷するための準備だ。
「餌を引く(食べきる)のに冬の時期は10日くらい見とかなあかんので、ギリギリの時に箱を(売り蜂用の3枚箱に)入れ替えて出荷することになりますね。桑名の7箇所の蜂場に300群がすわっとるんです。3月中旬には桑名の蜂場は(売り蜂を出荷し終えて)空になって、そこに志摩から元群が入ってくるという形になるんです」
続いて正浩さんが、初夏の採蜜期の光景を思い出したように話し始める。「うちの採蜜はすごいです。とにかく速いですから、ロボットのように動いて、1日に150群を採蜜して一斗缶80本というのがあります。300群の蜂で一斗缶500本の蜜を採ってくるのやからね」。正浩さんが試行錯誤の末に完成させた効率的な採蜜システムへの自負が伝わる。

志摩半島のあづり蜂場に到着し正浩さんが3人分の燻煙器を準備する
正浩さんと英幸さん、それに従業員の山田淳一(やまだ じゅんいち)さん(41)の3人が、一列になって並べられた巣箱の列に沿って1箱ずつ内検している。早く終わった者から順に列の後ろに回り次々と移動する。3人共、見事に同じペースを維持しているため、何かのゲームをしているように次々と巣箱を移動する。ひとり一人が養蜂家として責任を持って内検をしている様子が伝わってくる。内検を終えた後の蜂場を見ると、巣箱の蓋の上に小石が載せてあるのに気付いた。蓋の中央に小石を載せてある場合は、勢いがない印で巣板2枚出しの群。小石がないのは順調な群で3枚出し群、蓋の角に小石が載せてあるのは勢いのある印で4枚出し群だ。基本的には、出荷の日までに全ての群を3枚出し群に調整しなければならない。
「花粉交配に出す3月の一発目は花粉の多い古巣の方を蜂が好むんですが、5月になれば新巣でも大丈夫。3月半ばになってビシャガキ(ヒサカキ)の花粉が入り始めると貯蜜巣を抱かせるんです。ビシャガキの花粉が入ってくるということは、繁殖期に入っているということなんで貯蜜巣を抱かせる訳ですね。蜜蜂にとってひと冬寝かせた貯蜜はメインディッシュなんですよ。花粉が入って蜜蓋を掛けた熟成蜜ですから」

あづり蜂場での内検が終わり英幸さんと山田さんが内検の結果を確認する
従業員の山田さんが舘養蜂場本店で働き始めて12年になる。公募の求人に応募したのだと言う。6年前に英幸さんが帰ってきて、その一年後に央貴さんが帰ってくるまでは、正浩さん夫妻と3人で蜂場を切り盛りしていたので、山田さんは従業員というよりすっかり一人前の養蜂家の役割を果たしている。
「もともと生き物が好きだったし生態にも興味があったんですけど、養蜂の世界に入ってみて採れる蜜の量がすごかったのと、季節によって異なる花の蜜が採れるというのも新鮮でした。それに、ちょっとした工夫で採れる蜜の量が増えたり、蜂が活き活きするのは面白いですね。ぼくは仕事のついでに色々な生き物を探してみたりしているんで、養蜂の仕事を楽しんでいますね。魚と昆虫が好きというのがあるんで、ここで働く前は琵琶湖のアユの養殖をしたり、和歌山の水族館の手伝いに行ったり、それに熱帯魚のお店で働いていたこともありました」
Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi