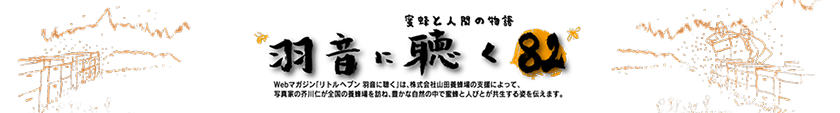創業は大正元年 曾祖父の松次郎

港蜂場で仕事を始める前、英幸さんが餌として与える砂糖水を運ぶ

「煙を掛けた時に上がってくるような蜂は要注意」と正浩さん
翌朝は、午前5時20分にホテルまで正浩さんがトラックで迎えに来て、元群が置いてある志摩半島の蜂場へ向かった。英幸さんと山田さんも軽トラックで同じ蜂場へ向かっている。まだ夜明け前、辺りは真っ暗だ。
「毎朝、4時には起きてしまう。これは蜂屋の習性やな。親父は8人兄弟の長男。男2人女6人。その親父が『今年の山は活気があるな』という表現をするんです。夜が明けて日の出前の薄明かりの中で遠くの山を見ると、その年の花の善し悪しが感じられるんでに」
車窓から夜が明け始めた遠くの山々の朧気(おぼろげ)な風景を見て、記憶の底に眠っていた父親の言葉が不意に思い出されたのかも知れない。それと同時に三重の方言が混じってくる。言葉は不思議だ。
志摩半島へ向かうトラックの中で、正浩さんの話が続く。
「私は大学を卒業して5年間はサラリーマンをしていましたね。(養蜂を)やり始めたのは27歳から、35年前ですか……。実は、その頃に親父が脳梗塞で倒れて養蜂場をどうするかという問題があったのと、私たちが結婚して間もない頃で子どもを育てるのに産休も無い時代ですから……、一方で、その頃は、蜂屋がどん底の時代でした。売り蜂の値が安かった。うちの親父は昭和5年生まれで、若い時にはええ思いもしているんですよ。昭和34年に蜂蜜が自由化になるまでは、昭和25年に一斗缶が一万円したと親父が言っていましたね。小学校教員の初任給が4000円の時代ですからね。うちの親父は91歳で3年前に亡くなりましたけど、養蜂業としては私で4代目。創業は曾祖父の松次郎(まつじろう)で大正元年に始めています。2代目が祖父の一十仁(いとじ)で、3代目が親父の幸弘(ゆきひろ)、そして私なんです。私が養蜂を始める時に親父に言ったんです。俺のやり方に口を出さんでくれって。親父の弟も養蜂をやっていましたから、叔父の所に1年間だけ修行に行って勉強したんですが、私が独立してから親父はひと言も意見は言いませんでしたね。ぴたっと養蜂の現場から手を引きました。あれはすごい」

港蜂場は雑木に囲まれているため風は吹き込まない
「転飼養蜂として舘養蜂場本店が北海道に初めて渡ったのは昭和16年、祖父の一十仁の代からでした。貨車に巣箱を載せて一週間かけて北海道へ行ったらしいです。貨車の中で火を焚いて七輪で食事を作って、北海道ではほとんどテント生活だったらしいですよ」
正浩さんは25歳の時に、同じ小学校に通っていた時子さん(62)と結婚した。高校は別だったが通学電車がたまたま同じ車両だったことから会話を交わす仲になったのだと言う。その後、養蜂の世界に入り、「夫婦だけで北海道へ行き始めた頃は相当いじめられましたね」。
「三重県は今、専業養蜂家が8軒なんですけど、私が始めた当時は60軒くらいありましたね。北海道も養蜂家がひしめいていました。蜂場の権利は一代跨ぐとなくなりますし、蜂場を3年空けると蜂場権はなくなる。そんな理由もありましたけど、うちの養蜂場としては北海道を休むということは絶対にできない」
言葉の端々に北海道の蜂場は絶対に守り抜くという覚悟が伝わってくる。
Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi