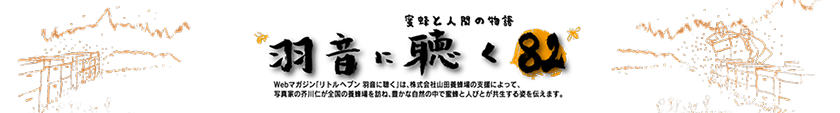森忠名神明神社 拝殿から本殿を望む

舘養蜂場本店の店舗前に聳える村社天皇八幡社の御神木芳ヶ崎のクロガネモチ
舘養蜂場本店の斜め前に「芳ヶ崎(はがさき)のクロガネモチ」が枝を大きく四方に広げ傘状をなしている。幹周りは3.25m、樹高が18mだ。資料によると樹齢は300年以上とあり、桑名市文化財に指定されている。このクロガネモチは舘養蜂場本店と境内が隣接する村社天皇八幡社の御神木として祀られている。幹の周辺は金網で囲われ、すぐ脇の細い生活道路に立って北北東を望むと村社天皇八幡社の鳥居を通して拝殿と本殿が一直線に見える。現在では変哲のない車の行き交う生活道路になっているが、古くは参道であり、その傍に聳える「芳ヶ崎のクロガネモチ」は、村社天皇八幡社の参拝者に憩いの木陰を提供していたことだろう。

左の石柱は伊勢大神宮遥拝所 右は神武天皇明治天皇遥拝所
る。現在では変哲のない車の行き交う生活道路になっているが、古くは参道であり、その傍に聳える「芳ヶ崎のクロガネモチ」は、村社天皇八幡社の参拝者に憩いの木陰を提供していたことだろう。
つまり舘養蜂場本店の在る地域は、古くから栄えた集落の中心地だったと思われるのだ。その名残なのか、舘正浩さんが呟くように話してくれた「私が子どもの頃は、この狭い道をバスが走っていましたからね」という言葉にかつては幹線道だったことが伝わるし、近くの四つ角には三重北農協七和支店や桑名七和郵便局が現在もあり、生活に必要な街の機能が集まっている。
芳ヶ崎のクロガネモチの傍を通る生活道路と村社天皇八幡社鳥居の前で交わる舘養蜂場本店前の道を南東の方角へ歩いた。この道は古くから濃州道と呼ばれ、桑名市三ツ矢橋町から濃州(今の岐阜県)へ向かう街道である。
歩き始めるとすぐ右手に、大きなタンクを備えた建物があって看板にヤマモリ株式会社桑名醸造所桑名工場とある。醤油、つゆたれ、レトルト食品の加工工場のようだ。工場前をやり過ごし少し進むと、空き地の横から左へ大きくカーブして上る坂道があり、カーブの内側に小さな新しいお堂が見えた。お堂の建つ周辺の土地は整地して間もない感じで、少し荒れて草の一本も生えていない。ガラス戸が外の風景を反射して中をよく見ることは出来ないが、赤い布と活けた花が見える。そこにちょうど白い犬を散歩させて60歳ほどの女性が坂道を上って来たので尋ねた。
「お地蔵さんだと聞いていますよ。このお堂は以前は、この小径の反対側にあったんですけど、土地を売られた方が私有地の中にあるからと移されたんだそうです。私は名古屋からここに嫁に来たんですけど、ここらは神社がともかく沢山ありますよね。どうしてだかご存じですか」
私がカメラを肩から提げ、ノートを持っていたので、何か調査でもしていると思われたようだ。逆に質問されて神社の存在が気になり始めた。お地蔵さんの坂道を下り、元の道の四つ角を再び南東へわずか10mほど歩くと、左側に森忠名神明神社の大きな石柱と鳥居、それに灯籠がある。鳥居と灯籠には大正十三年十月の文字が刻まれている。鳥居を潜り民家の間に挟まれた参道を歩くと、やがて石段になり上に立派な拝殿が見える。石段を上り切ると広々とした境内の右端に社があって、小さな宮形と大きな御幣が祀られている。しかし、神様の名は分からない。境内の端は崖になっていて、石柱が2本並んでいる。右の石柱には神武天皇明治天皇遥拝所、左の石柱には伊勢大神宮遥拝所と刻字されている。この見晴らしの良い高台から望むと民家の屋根瓦が連なり、一軒一軒の人びとの暮らしに思いを馳せることができる。遠くには正浩さんが自慢していた養老山地と濃尾平野の境界に延びる断層帯の丘陵地も見えている。
さて、目的の森忠名明神神社の本殿は、拝殿から続く板塀に囲まれていて近づくことができない。拝殿は厳重に鍵が掛けられガラス戸越しに本殿を覗き見ると、幾重ものガラス戸に外の景色が重なり合って映し出され、偶然に視野に入ってくる太陽の輝きも相まって、幻想的な空間を創り上げていた。

ヤマモリ株式会社桑名醸造所桑名工場
さらに濃州道を南東へ歩くと、街道は左右に緩やかな曲線を描きながら民家の間を抜けている。正浩さんが話していた時代を想像して、民家の軒先をかすめながらボンネットバスがこの道を走っていた光景を思い描くと、僅か半世紀ほど前の時代だが、時計の針はゆっくりと進み、子ども達の笑い声が遠くから風に乗って聞こえてくる。そんな幸せの時代を思い浮かべる光景だ。もう少し歩けば、多門院安渡寺や星川神社が在ることは道路脇の看板で分かっていたが、森忠名明神神社の幻想的な空間を撮影するのに精魂を使い果たし、そこまで歩く気力が出てこない。最後にどうしても舘養蜂場本店と隣接する村社天皇八幡社の境内を歩きたいと思った。
村社天皇八幡社の大きな刻字と大正十四年十月建立と刻まれた石柱を右に、大きな石灯籠を左に見て参道に入る。10mほど歩いて石造りの鳥居を潜る。良く見ると、笠木と呼ばれる鳥居の一番上に渡された石の端が、舘さん宅の敷地に突き出ている。正浩さん曰く。「境内の奥に建つ本殿の中心が、鳥居の真ん中から真っ直ぐに見えなければならない」とのことで、舘家の敷地に鳥居の端が入るのを承諾したらしい。鳥居を潜りながら目を上げると、確かに真正面に拝殿と本殿が建っている。鳥居の柱には舘幸次郎の名が刻まれていた。幸次郎は舘養蜂場本店の創業者松次郎の弟である。村社天皇八幡社の境内に舘さんの自宅があるのか、舘さんの敷地に村社天皇八幡社が建っているのか、そんな隣同士の関係では、付き合いも深くならざるを得ないのだ。ちなみに本殿横に祀られている順正稲荷神社の赤い鳥居には舘養蜂場本店舘正浩の名が書かれてあった。
現在では台地の上を走る国道421号線に流通の主な機能は譲っているが、濃州道は歴史を刻んだ街道だったことが伝わってきた。森忠名神明神社の鳥居と灯籠に刻まれた大正十三年十月の文字と村社天皇八幡社石柱に刻まれた大正十四年十月建立の文字。それに舘養蜂場本店の初代松次郎が養蜂を始めた大正元年。「大正デモクラシー」や「大正ロマン」。それと第一次世界大戦に翻弄され乱高下した景気。短く騒々しい時代だったが、それだけ民衆に活気がみなぎっていた時代だったのだ。現在も、そんな時代を思い起こさせる濃州道に魅力を感じた。

村社天皇八幡社拝殿

Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi