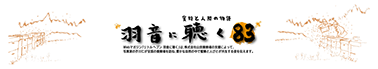蜂が田んぼに水を飲みに

内検する継ぎ箱の前に餌として加える蜜巣板が準備されている
「一旦北海道に帰った後、2月20日に五島市に来て、全体を一回は内検しましたけど、本格的な内検は今日が初めてなんで、少し体にきましたね」と、純一さんは少々お疲れの様子だ。午後3時半には、この日の内検を終了した。その後、事務所兼自宅で話を聞かせてもらう。
「ネオニコチノイド系農薬が出だしてから、秋まで残る蜂の数が極端に少なくなったので、その影響だと思っているんですけどね。証明する術はないんですよね」
北海道ではカメムシ防除策として(摂取すると神経細胞に作用する毒を持つ)ネオニコチノイド系農薬をドローンなどで散布している。農協などを通じて散布する日時が事前に養蜂家に連絡され、蜜蜂の避難を呼び掛けられるが、直接暴露だけでなく水に溶けて植物にも取り込まれ、長期間分解されない残留性もあるため、避難が万全の対策とは言えないのが実情だ。主にEUの国々では、ミツバチの方向感覚などに障害が起きて巣に戻れなくなる蜂群崩壊症候群と呼ばれる現象が起きて、ネオニコチノイド系農薬との関連が疑われている。そのためEUでは2018年から幾種類かのネオニコチノイド系農薬の使用を規制しているが、我が国では規制はされていないため、純一さんが現状を憂いているのだ。

崎山蜂場に到着して、純一さんが燻煙器を準備する
「それに除草剤グリホサートが手軽にホームセンターなどでも購入できる状態ですが、蜂が田んぼに水を飲みに行くじゃないですか。蜂は死なないまでも、農薬を巣箱に持って帰ってくると、蜂蜜の残留農薬基準値の0.05ppmを超えるかも知れないと思うと心配ですよね」
養蜂家なら誰にでも共通する不安なのだが、一人ひとりの養蜂家では対処の方法がない問題だ。科学的に因果関係を証明できなくても、長期間に亘る微量汚染の蓄積による被害が疑われるならば、何らかの手を打って推移を見守る国の対策が必要だと思う。アメリカの生物ジャーナリストであるレイチェル・カーソンが1962年に発表したベストセラー『沈黙の春』を引き合いに出すまでもないが、儚い命の蜜蜂は人類よりもずっと軽微な汚染で命を奪われ、それが人類への警鐘となることを真摯に受けとめたい。

蜜蜂の状態を見るのは純一さん、使わない巣板や蜜巣板を運ぶのは珠江さん




Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi