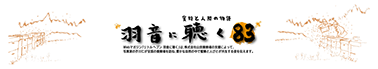子ども連れでラブホテル

産卵は始まっているか、餌は足りているか、蜂数は多いか等を確認する
純一さんが気分を変えようという表情で話し始めた。
「小さい頃には、俺は絶対蜂屋にならないと思っていたけど、大学に行って春休みや夏休みに養蜂を手伝っていると、春の蜂がみるみる増えていくのを見たり、蜜が思っていた以上に採れるのを体験したりすると、蜂屋に対して小さい頃とは違った印象を持つようになりましたね。その頃から農家が時季外れの果物を作るようになって、メロンでもイチゴでも交配の仕事が始まって、自然界に貢献していることを感じると、蜂屋も良い仕事だなと思えるようになってきました。小さい頃は親がやっていた仕事だからと、毛嫌いしていた面はあったかも知れませんね。最近は時間にもゆとりが持てるようになって、北海道から五島に巣箱を運んだ後、一か月くらいの間で越冬の準備を終わらせると、12月20日を目処に北海道に帰るんですけど、ここ何年だろう、北海道へ帰る時にはトラックに蜂は積んでいないし、ゆっくり観光しながら帰っているんです。何年前だろう舞鶴から小樽へのフェリー航路が、海が荒れて乗れない時がありましてね、それが切っ掛けで、折角だから京都観光をして帰るかということで……」
ここまで純一さんが話しをすると、何やら思い出したように珠江さんが話を引き取った。

珠江さんが巣箱を腰に乗せて運ぶ
「でも、トラックで帰っているから、一般の駐車場には停められないで大変なこともあったよね。あれ何年前だったかね。暮れだからホテルが取れなくて、子ども連れでラブホテルに泊まったこともあったよね。あの時にはホテルにトラックを停めさせてもらえなくて、ホテルの世話で近くのスーバーの搬入口に停めさせてもらったよね。その上、朝、フェリーに乗るのに出発しようとしたらパンクしていて大騒ぎ」
2人の話を聞いていると、越冬先の福江島から北海道の本拠地まで晩秋から5月の連休明けまでに何度も往復する苦労ばかりを想像していたが、楽しみもあることが伝わってくる。それだけ精神的にも経済的にも余裕が出てきたということなのだろう。

北海道から移動してきた巣箱を開けると、寒さのため巣板の上部に円形になって蜜蜂が死んでいた




Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi