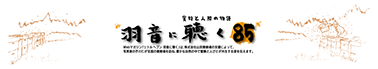全部アカシアになったらすげぇな

鳴尾の熊野神社大スギの傍で橋詰将太さん
打合せが終わると「助手席に乗ってください。案内します」と、橋詰さんが軽トラックに私を促す。
「嬬恋村鎌原(つまごいむら かんばら)地区は、およそ250年前の浅間山天明の大噴火の火砕流や土石雪崩で壊滅していたんです。最初は焼け野原だった場所をおよそ100年前に開拓した地域で、僕は嬬恋村で生まれ育ったんです。入植者は10軒以上居たんですけど、今は一軒だけ。じいやん(祖父)の父ちゃんが開拓した土地。この辺は熊だらけですね。(蜂場に)電柵は必須ですね。自分は何回か引っ越ししたけど、浅間山の周りから離れられないですね。今は、(長野県)小諸(市)から通って来ています」
運転しながら、地域の歴史とも自己紹介とも思える橋詰さんの話が続く。
両側にカラマツの並木が続く一直線の舗装道路から畑の中の小径に入る。少し進むと右前方に小さな家が2軒並んでいた。「ばあやん、居ないな」と橋詰さんが呟く。その家を横目に先へ進むと電柵で囲った広場に巣箱が10箱ほど置かれてあった。鎌原(かんばら)蜂場だ。蜂場奥の茂みに大きなトチノキが一本。橋詰さんが惹かれたようにトチノキに近づき、見上げたまま私に話し掛ける。「今、トウダチ※している。今年は流蜜が良いかも知れませんね。去年も一昨年(おととし)も霜にやられました。近くに鎌原城という小さいお城があったみたいです。今、フジが盛りですね」
※トウダチ:薹立ち(花芽がついて花茎が伸びていること)

暑さのため巣箱から溢れ出した蜂を刷毛で巣門へ導く
橋詰さんの頭脳の回転に、私が付いていけない。恐らく、橋詰さんの頭の中では、地域の歴史や生まれ育った故郷の思い出と、目の前に広がる現在の光景が一つの物語として展開しているのだろう。言葉として発せられるのは、その断片なのだ。橋詰さんの頭の中で繰り広げられている物語を想像しながら、私は必死で、彼の言葉を追いかけていた。
軽トラは鎌原蜂場を出た後、カラマツ並木が続く真っ直ぐな舗装道路を走り、視界が開けた辺りで再び未舗装の農道に入った。遠くに浅間山を望む畑の脇を通る。
「ここは同級生がズッキーニを植えている畑。交配用に5群の蜜蜂を置いています。ズッキーニの他にキャベツやトマトなど夏野菜を植えている同級生の畑。そば屋なんです。嫁に行っちゃってるね。畑に大型機械を入れるんで、土壌が流出しているんですよ。あと50年で(野菜を)作れなくなる。天明3年の大噴火の時、火砕流が流れた畑はキャベツには向かないね。石が出てキャベツには向かない。自分、けっこう地元が好きで、同じ嬬恋村田代地区で育ちました。キャベツ村ですよね。自分が小学生の頃にパイロット事業で嬬恋村のキャベツ畑が倍になったんですよ」

巣箱の中は高温になっているようで、蜂が外に溢れ出す
同級生の畑では軽トラから降りないまま、カラマツの林が続く一直線の舗装道路を浅間山の裾野へ向かう。
「これ全部、アカシアになったらすげぇなと思っているんですよ。養蜂を始めて気付いたんですけど、アカシアのような外来種は人間が手を入れた所にしか生えないですね。手付かずで根っからの自然の所には生えないんですよ」
カラマツの林を過ぎてカーブを大きく描いて緩やかな丘陵が広がる台地に出ると、定植したばかりの苗が幾筋もの緑色の線を描くキャベツ畑が広がる。浅間山がすぐ目の前に大きく聳(そび)えている。
「山は杉の木ばかり。良かれとやっても結果が良くない。世の中、そわそわしている感じがあって、弾け飛ぶ寸前のように見えますね」。橋詰さんの言葉が世の中のどんな現象を指しているのかは不明だが、確かに、足の裏でしっかり大地を踏みしめて生活している実感が希薄になっているように思えて共感できる言葉だ。

昼ご飯は木陰にシートを敷いて弁当を食べる




Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi