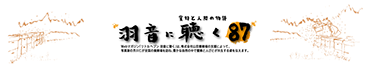面布も手袋も着けない

尾奈上蜂場で内検を終えて石川さんが餌の砂糖水を与える
取材2日目は晴天。早めに店舗に行くと、店舗前の駐車場で清掃をしている従業員の中に石川さんの姿もあった。清掃を終えると朝礼だ。2階ホールに石川さんと一緒に入ると、テーブルの上に「月刊朝礼」の抜粋コピーと単行本『考えてみる』(大久保寛司著)が並んで置いてある。私には苦手な雰囲気だ。参加者の中に、昨日はシフト勤務の休日に当たっていたため会うことができなかったが、養蜂部3人のうちの一人、細谷 一真(ほそや かずま)さん(29)も居た。細谷さんは北海道樺戸郡月形町の出身。「小さい頃から虫が好きで、大学で昆虫を研究したい」と思っていたが希望の大学には合格できず一年間浪人した。しかし、大学進学を諦めてネットで就職先を探す中で小森養蜂場に出会い、3年間働いた。その後、大学で昆虫を研究したい夢を諦めきれずに、再び受験勉強をして、蜜蜂の研究で名高い玉川大学生産農学科に入学。4年間蜜蜂を研究して「カフェインが雄峰に及ぼす影響」というテーマで卒論を提出し、新卒で長坂養蜂場に入社して1年半になる。

内検をしている石川さんの左手中指が腫れている。蜂に刺されたようだ

本坂蜂場で内検をする石川裕児さん
「研究すればするほど蜜蜂って面白いなと思って……。蜂を見ていると、その度に新しい発見があって奥が深いですよね。自分が熱中できる仕事に就けているのは幸せだと思います」
朝礼の後、細谷さんの運転する軽トラに同乗させてもらって最初に行ったのは尾奈上蜂場。74群の巣箱が置いてある。防風林に囲まれた蜂場の周りは、ほとんど三ヶ日みかんの畑だ。わずかに色付き始めたみかんがたわわに実っている。細谷さんが燻煙器と餌の砂糖水のタンクを持って内検を始めた。細谷さんは面布も手袋も着けないで作業をしている。「蜂を扱う時は素手で優しくしろというのが修業させてもらった小森養蜂場の社長の教えでしたから……。面布は着けることもありますけど、秋のこの時期に刺されることはないですから……」と、細谷さん。手袋を着けて蜂を扱えば、繊細さに欠けるのは確かだ。
追いかけるように石川さんが2トントラックでやって来た。石川さんは面布を着けてはいるが作業は素手だ。巣箱へ向けて歩き始めて「あっ」と小さな声を出した。「燻煙器を忘れた」と告げる。面布や手袋がなくても内検はできるが、燻煙器は必須だ。石川さんは燻煙器を取りに会社へ帰り、間もなく戻ってきた。

本坂奥蜂場で内検をする細谷一真さん(左)と黒澤和さん




Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi