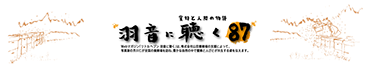長坂養蜂場のマスコットキャラクター「ぶんぶん」が、
お客さんを歓迎する


長坂養蜂場店舗入口の看板
取材3日目の朝はぎっくり腰で、夜中に用足しに行くにも四つん這い。一泊目の朝から違和感はあった。ホテルのベッドが合わなかったようだ。当初の予定だと、ここのページは株式会社長坂養蜂場養蜂部マネージャーの石川裕児さん(56)が「三ヶ日みかん蜜がうちの命」と強調していたので、その蜜源となっている「三ヶ日みかん」について伝えることにしていたが、取材はできず。資料を読み解くことで「三ヶ日みかん蜜」の背景にある「三ヶ日みかん」の奥深さを伝えます。
三ヶ日みかんの歴史を辿ると、江戸時代中期に紀州の那智から「紀州みかん」の苗を持ち帰り、現在のみかん栽培のきっかけを作った人物として山田弥右衛門の名が出てくる。もう一人、江戸時代後期に三河から現在の食用の主流となっている「温州みかん」の苗木を持ち込み、栽培を始めた加藤権兵衛の名も出てくる。更にもう一人、1918(大正7)年に造成が開始された三井家の三井高精(たかきよ)らが出資した柑橘事業の拠点「開南組柑橘園」の専任技術者として1920(大正9)年に赴任した中川宗太郎が、栽培技術の普及に貢献したと資料にある。

長坂養蜂場店舗に置いてある蜜巣板と蜜蜂の標本、外には巣箱も置いてある
静岡県浜松市浜名区三ヶ日(みっかび)町は、浜名湖の北側に位置し、土壌は肥料分が少なく砂礫質で水はけが良いため、みかん栽培に適している。しかし、痩せた土地で美味しいみかんを収穫するためには栽培技術が必要で、その先頭に立って技術指導したのが当時の農商務省農事試験場園芸部から専任技士として招かれた中川宗太郎だった。宗太郎は、中泉農学校(現磐田農業高校)を卒業して、農業試験場の見習生を終えたばかり。それまで「苗木」「幼木」でなければ難しいとされていた常識を覆して「成木」の移植を、それも移植は春でなければと考えられていたのに「秋に移植すれば、冬の間に木が土に馴染んで春の芽吹きが早い」と「秋植え」を行うことで、栽培の難しかったみかん畑を回復させていく。その背景には、剪定技術や病害虫の防除、肥料の適切な施しを行い、木の管理を徹底することが必須だった。
また、冬場の季節風「遠州の空っ風」と呼ばれる北西の強い風によって、枝が折れたり収穫期の実が落下したりする対策として、マキの木をみかん畑の防風林として周囲に植えることや、ムシロなどでみかんの木を囲って風をしのぐ方法も考えだし、収量向上に結び付けた。
このような取り組みとその成果は近隣のみかん農家に大きな影響を与え、宗太郎の栽培技術を学びたいと、こぞって指導を受けたことで三ヶ日みかんの産地として定着し広がることになる。

長坂養蜂場のマスコットキャラクター「ぶんぶん」のラッピング列車が天竜浜名湖鉄道を走る
もう一つ、宗太郎が行った改革に販売方法がある。従来は、みかんが色付き始める前の7月か8月頃、商人が実の生り具合を見てその年の収量を予測した上で相場を勘案し、ひと山(畑)ごとに農家から買い付ける「立木売り」と言われる商人に有利な販売方法だった。それを宗太郎は、実際に収穫されたみかんの重量を計測して販売価格を決める方法に改めた。その結果として、農家それぞれが商人と取引をしていた方法から、農家が共同出荷する方法に変更され、農家の意志が反映する販売価格を設定ができるようになった。
90年前の1935(昭和10)年に長坂養蜂場初代の長坂喜平さんは、現在地とは少し離れた同じ三ヶ日町内で養蜂を始めている。「三ヶ日みかん」の歴史を辿ると、宗太郎が赴任して15年後だ。宗太郎が赴任する直前には米騒動が起こっており、経済的混乱でみかん価格が低迷したことで現金収入を得やすい養蚕に転じようと、みかんの木を伐採して桑を植える農家が続いた時代もあった。初代喜平さんが創業した当時は、三ヶ日地区の農家がみかんを主力に復興しようとする途上の時代である。90年後、長坂養蜂場の主力蜂蜜が「三ヶ日みかん蜜」になるとは、初代喜平さんは想像もできなかっただろう。





Supported by 山田養蜂場
Photography& Copyright:Akutagawa Jin
Design:Hagiwara Hironori
Proofreading:Hashiguchi Junichi
WebDesign:Pawanavi